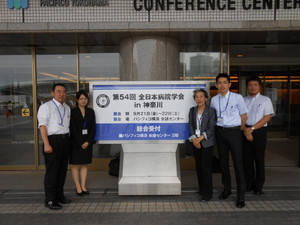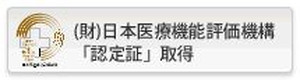「第20回 日本慢性期医療学会(福井大会)」に参加しました
11月8日、9日にわたって福井市で開催された「第20回 日本慢性期医療学会」に参加しました。当院からは8題の演題を出し、看護師、介護福祉士、診療放射線技師、作業療法士、社会福祉士、等、多職種が参加し発表を行いました。
今回は、日本の超高齢化社会を支えるため、「慢性期医療」の「復興」「復権」への道を議論し発信していく、「慢性期医療ルネッサンス」が大会のテーマでした。医師で宇宙飛行士の向井千秋氏による記念講演も行われました。
全国の慢性期病院から代表者が集まっていることから、各医療機関の発表は充実しており、大いに勉強や参考になる内容でした。
こうして、全国規模の学会に参加し、業務における内容を発表できることは、当院としても、発表者にとっても、レベルアップや今後の改善につながる、非常に重要なことであると思います。
当院では、この日本慢性期医療学会をはじめとした、院外の学会や勉強会等への参加を積極的に行い、知識・技術の習得、医療の質の向上を図っております。
= 以下に、今回の当院の演題発表8題の発表概要を記載します =
![]() 当院地域連携室の活動~訪問活動を通して~
当院地域連携室の活動~訪問活動を通して~
当院地域連携室の特色として、他医療機関などの訪問活動にも積極的に力を入れており、入退院調整のみならず、訪問活動の強化・対策を他部署と共に行っています。今回は、今後の訪問活動のあり方について検証した内容を報告しました。
![]() 経管栄養に関する業務改善の一例~加圧バッグの導入~
経管栄養に関する業務改善の一例~加圧バッグの導入~
経管栄養とは胃瘻または鼻からの栄養チューブを通して水分や栄養を摂取する方法です。
今回、加圧バッグの導入が実現し軌道にのった結果、注入時間、コスト面、職員の手の痛みなどの改善が見られたので報告しました。
![]() PEG前CTにおける3D作成の評価とこれからの活用
PEG前CTにおける3D作成の評価とこれからの活用
今まで前検査として経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG)の腹部CT及び多断面再構成像(MPR)の作成を行っており、有効に利用できているが、患者や患者家族にもう少し、説明が理解できるように3D画像を作成し、当院職員で調査を行ったので報告しました。
![]() 災害時に当院ができること~東日本大震災のボランティアを経験して~
災害時に当院ができること~東日本大震災のボランティアを経験して~
昨年、3月に東日本大震災が起こり、その後、4月より1ヶ月間、東北の被災地でボランティアを経験し、悲惨な現状、いろいろな体験をしたので、有事の際、当院として何ができるのか、被災地の実状を踏まえ、今後の体制つくりなどを報告しました。
![]() スキンケアの取り組みと職員への意識付け
スキンケアの取り組みと職員への意識付け
スキンケアには様々な方法があげられているが、オリーブオイルは人の肌に馴染みやすく、皮膚をケアし再生するといわれています。今回、定期的なオリーブオイルの塗布を行った結果、患者の乾燥の改善が見られ、職員の意識向上へつながったので報告しました。
![]() 申し送り廃止にむけての取り組み
申し送り廃止にむけての取り組み
今まで申し送りに時間を要したため、時間短縮に向けて、スタッフ間で話し合いの場を設け、具体策をあげ、短縮の目標を設定して、時間測定を行った結果、スタッフの意識の変化と申し送り時間の短縮、患者ケアの充実が図られたので、その経過を報告しました。
![]() 認知症高齢者への集団有効性の検討
認知症高齢者への集団有効性の検討
認知症高齢者の入院に伴い、身体面だけでなく精神面での介入は必須である。今回、当院の入院患者に集団レクレーションを実施し、機能的自立度評価表等や介入者の「気づき」「観察」に基づく観察記録を取り比較検討した結果を報告しました。
![]() 患者サービス向上への取り組み
患者サービス向上への取り組み
当院では、医療サービス委員会を中心に、患者サービスの向上を目指しています。従来の活動を見直し、より積極的に現場や患者を直接見ることによって、患者視点により近いサービスの実現を図っています。今後、更に活動やサービスの評価を行い、患者・職員ともに満足度を高めるべく、取り組みについて報告しました。