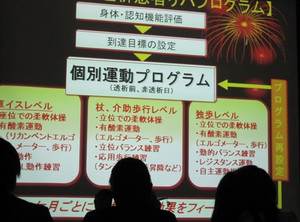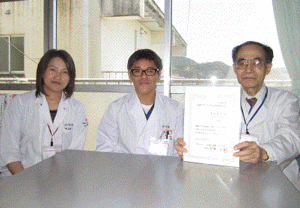こんにちは
一月になり外来患者様の中にも、インフルエンザの方が少しずつみられるようになりました
小学校や中学校では、学級閉鎖になったところもあるようですね
今回は、インフルエンザに感染しないように、また、他者に感染させないようにするためのアドバイスをご紹介します

まずはウイルスに接触しないように人ごみを避けることです。
ウイルスは感染した人の咳やくしゃみ等のしぶきに多く含まれていて、そのしぶきを吸い込むことで感染します。しぶきは1~2メートル飛ぶため、人ごみを避けることで感染のリスクを減らすことができます


また、ウイルスをまき散らさないように咳エチケットを守ることが大切です。咳・くしゃみをする際は、ティッシュやハンカチなどで口と鼻を覆って、人のいない方向を向くように心がけましょう
ウイルスに感染しないためには、手洗いうがいも重要です

ウイルスはドアノブや電車のつり革、受話器など、様々なものに付着しています。それらに触れた手で口や目に触ると感染リスクが高まります。外出先から帰った時、食事の前などは手洗いうがいを忘れずに行いましょう。また速乾性のアルコール消毒も併せて行うと効果的です
更に、加湿器を使って湿度を50~60%に調整したり、部屋の温度を暖かく保てば、ウイルスの活性化を弱めることができます
食事や休養に気を付けて、ウイルスに負けない抵抗力をつけることも大切です。
食事は栄養バランスを考えながら、たんぱく質やビタミン類、食物繊維などをしっかり取りましょう また、疲れていると体の抵抗力が落ちてしまい、ウイルスの攻撃を受けやすくなるので、意識的に心身を休めるように心がけましょう
また、疲れていると体の抵抗力が落ちてしまい、ウイルスの攻撃を受けやすくなるので、意識的に心身を休めるように心がけましょう
まだまだ寒い季節が続きますが、体調を崩さないようにお互い気を付けましょう

![]()