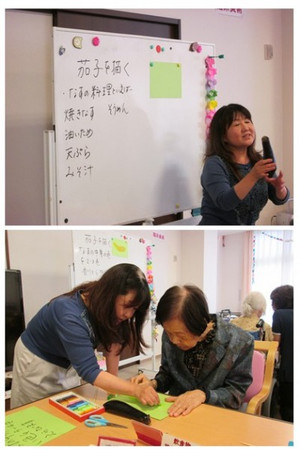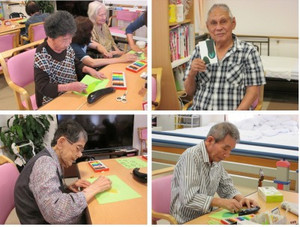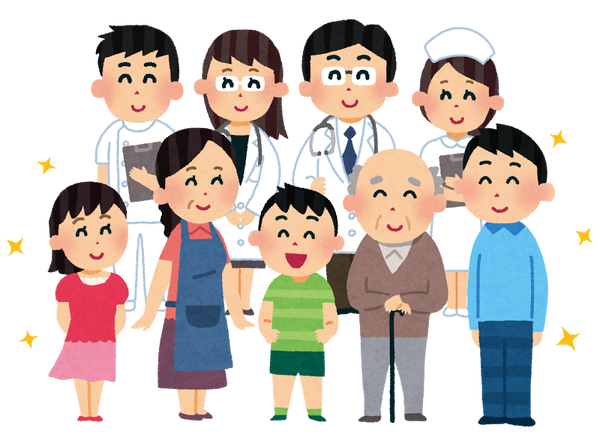臨床美術ってなに?
こんにちは!
今回は、国分中央病院の通所リハビリテーション(デイケア)で
取り入れています、「臨床美術」についてのご紹介です。
臨床美術ってなに?…初めて耳にする方も多いのでは
ないでしょうか。臨床美術とは、絵を描いたり、ものを
作ったりという創作活動が脳の働きを活性化させて、
高齢者の認知症ケアに効果があるのではないかという
発想から開発された、1996年に誕生した比較的新しい
取り組みです。専門知識を持った臨床美術士が、参加者
お一人お一人の個性や状態に合わせて、その人の意欲
と潜在能力を引き出していく独自のプログラムとなってい
ます。現在では、発達が気になる子どもへのケアや小学
校の授業、社会人向けのメンタルヘルスケアなど、幅広く
取り入れられているようです。
国分中央病院では月に1回、第2木曜日に臨床美術士
の先生をお招きし、通所リハ利用者様への取り組みを
行っています。「むずかいしいな~」「楽しいよ」「絵は苦
手なのよ~」など反応は様々ですが、先生のほか職員
もお手伝いし、それぞれに作品を完成させ、最後に参
加者全員で鑑賞会を開きます。「苦手だ」とおっしゃって
いた方も最後にはご自分の作品に満足され、お持ち
帰りになられます。
見学も随時受付けておりますので、どうぞお気軽に
お問い合わせください。
お問い合わせ先:国分中央病院/通所リハビリテーション(担当:假屋)TEL:0995-45-3085